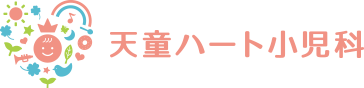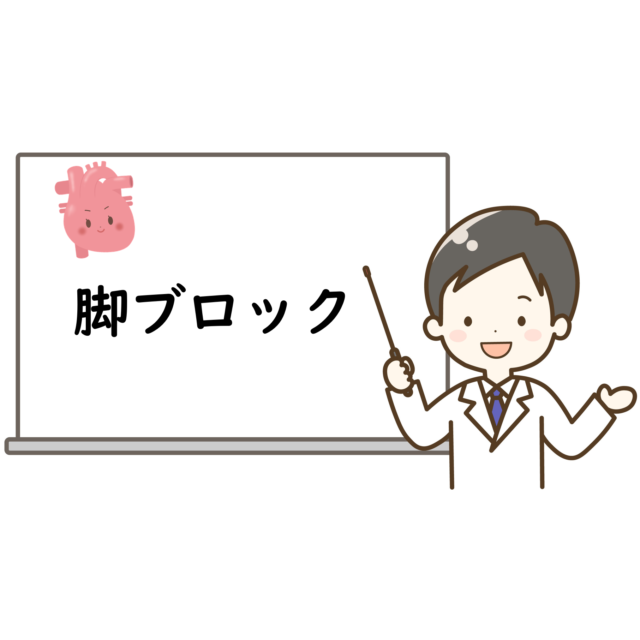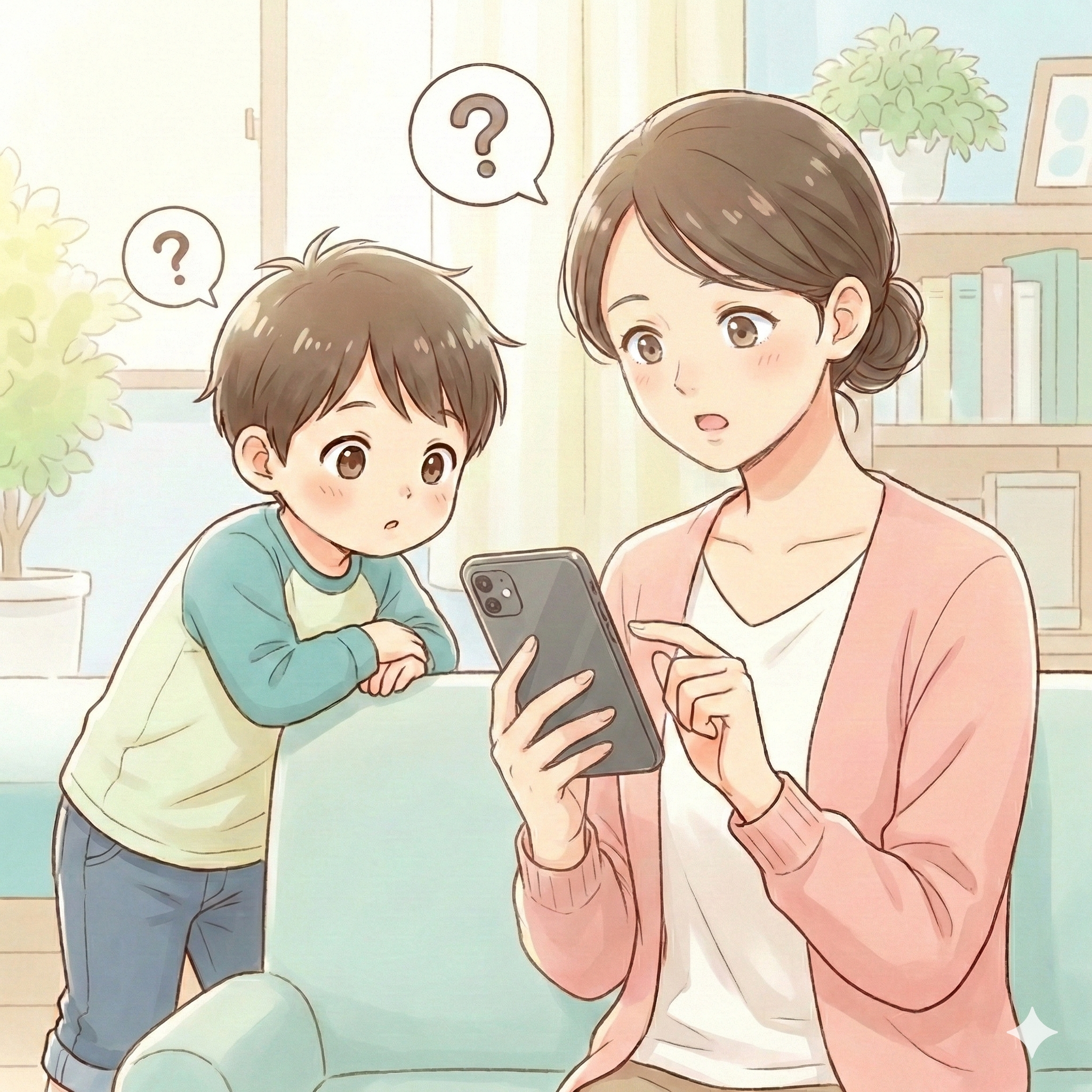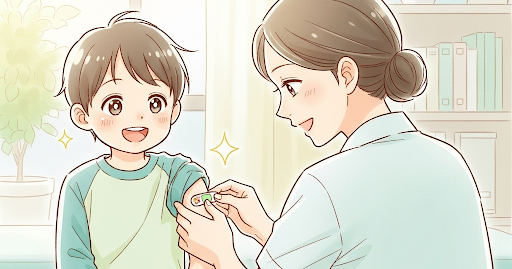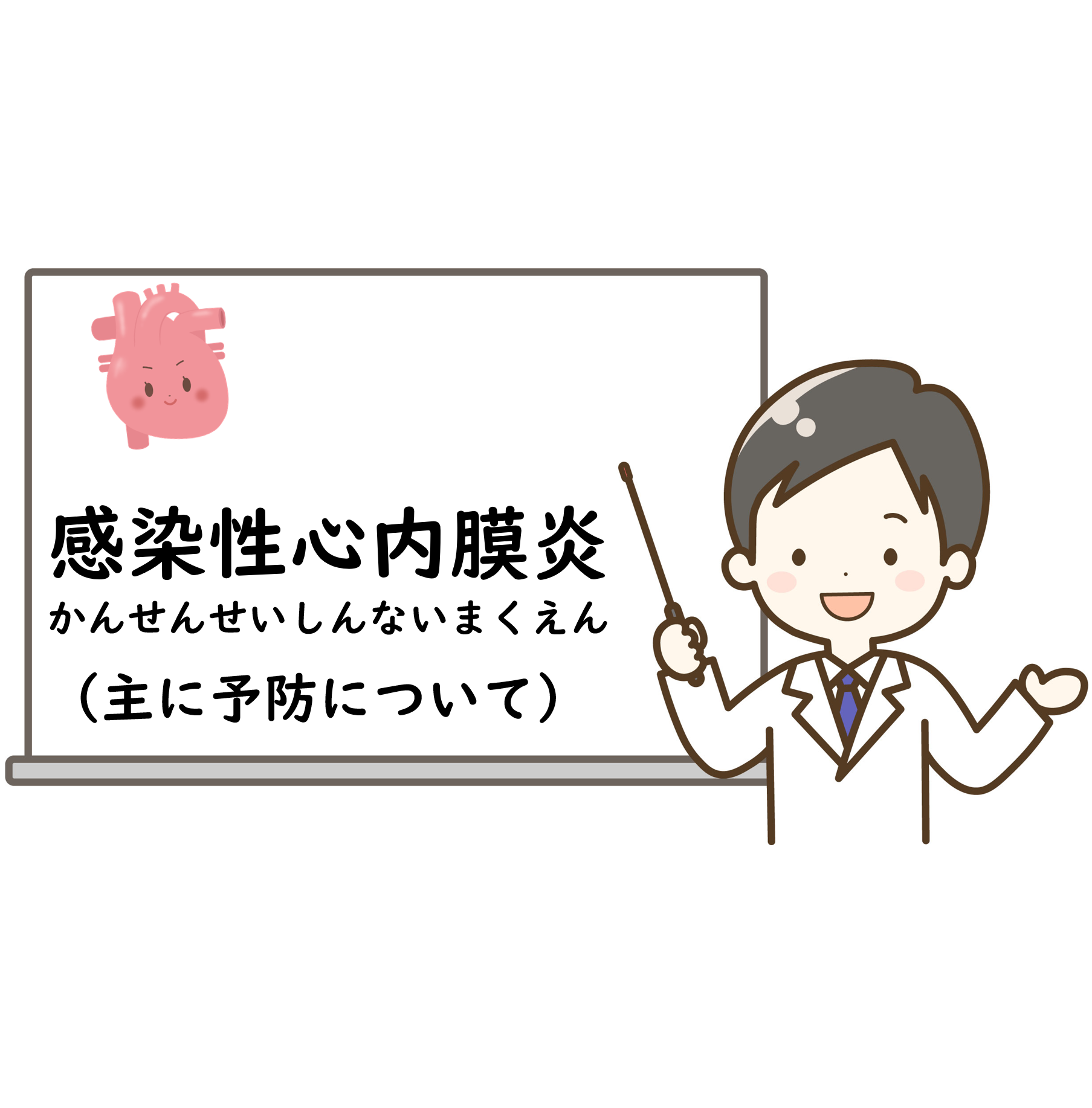

先生、うちの子、心室中隔欠損症と言われてるんです。
日常生活で気を付けないといけないことはありますか?

お子さんに心臓の病気があると、とても心配ですよね。
まず、定期的な通院は必須で、他に医師からの指示があれば内服、運動制限をしっかり行う必要があります。
それから、「感染性心内膜炎(かんせんせいしんないまくえん)」の予防も必要ですね。

カンセンセイシンナイマクエン?それって何ですか?何に気を付ければいいんですか?

たしかに、聞きなれない名前の病気ですよね。
ここでは、感染性心内膜炎について詳しくお話ししましょう。
【ざっくりと!】
・感染性心内膜炎とは、心臓や大血管の内側の面(血液が触れるところ、「内膜」と言う)に細菌(や真菌)が住み着く病気です。
・細菌が心臓の中の扉(弁)を破壊したり、細菌の塊が全身に飛び散るなどするため、有効な治療をしないと死に至る恐ろしい病気です。
・細菌は、虫歯の治療など、出血を伴う事態が生じた際に血液内に入り込みます。
・少量の細菌は血液に入り込んでも免疫系に排除されますが、先天性心疾患がある場合、感染性心内膜炎にかかるリスクが高くなります。
・虫歯にならない、歯科での治療をはじめリスクのある医療行為をする場合には予防的な抗菌薬内服を行う、などの対策をすることで予防することが出来ます。
・歯科では、「感染性心内膜炎の予防が必要な心臓病がある」と必ず説明してください。
・大量の出血を伴う処置をする1時間前に、「アモキシシリン」という抗菌薬を体重1 kgあたり50 mg(最大量2000 mg、成人量2000 mg)内服する必要があります。
【感染性心内膜炎とは?】
心臓や血管は、血液の通り道で、複雑な形をしたトンネルのような形をしています。そのトンネルの内側の面を内膜と言い、心臓の内膜を心内膜、血管の内膜を血管内膜と言います。心内膜や、大血管の血管内膜に細菌が巣を作って増殖する状態を、「感染性心内膜炎」と言います。
長引く高熱(時に微熱)や倦怠感などの自覚症状があります。通常のウイルス感染症と違って、咳嗽や鼻汁などの症状は通常みられません。熱は自然に下がることはなく、抗菌薬の内服で一時的に解熱しても時間が経過すればまたぶり返します。
また、細菌が心臓の中の扉(弁(べん)と言います)を破壊すると弁逆流が生じ、心臓への負担が大きくなると心不全になります。細菌の塊が心臓や大血管から全身に飛び散って全身あらゆる内臓の血管が詰まってしまい、血流不足から内臓の働きが阻害されてしまうこともあります(細菌塞栓)。脳梗塞などの重篤な状況になることもあります。
最低でも1-2か月間の入院・抗菌薬点滴が必要になり、緊急手術を含めた強い治療が必要になることもあります。それでも死亡したり、全身あらゆる内臓に後遺症を残したりすることがあります。適切な治療をしない場合の死亡率はほぼ100%という、恐ろしい病気です。
【どうして感染性心内膜炎になるの?】
本来血液の中には細菌はいません。人の体の表面には細菌が多数住み着いていますが、その細菌が体内に入り込むためには皮膚や粘膜などのバリアを侵入する必要があります。
例えば口の中は、どんなに歯磨きをきれいにしている人でも細菌が住み着いています。歯周病などで歯茎から慢性的に出血していたり、抜歯などの歯科治療で大量に出血する場合などに、細菌が血液に侵入します。
通常であれば、細菌が少量血液内に侵入したとしても、すぐに免疫細胞にやっつけられて消えてしまいます。何等かの原因で細菌が死滅せずに生き残り、心臓や大血管で繁殖してしまうと感染性心内膜炎となります。
【どんな人がなりやすい?】
先天性心疾患や弁膜症などがあると、通常よりも速い血流が見られることがあり、ジェット血流と言われます。(人の体内では通常2m/秒よりも速い血流が見られませんが、心疾患があると最大5m/s程度まで加速した血流が見られることがあります)
このようなジェット血流が心臓内や血管内の壁に吹き付けると、その場所は慢性的に傷んだ状態になり、細菌がやってきたときにそこを足掛かりに増殖すると言われています。
また、BTシャント、ラステリ手術など、人工物を用いた手術をした場合も注意が必要です。人工物には細菌が感染しやすいためです。
以下に、疾患ごとの感染性心内膜炎のリスクを記載します。
(感染性心内膜炎の予防と治療に関するガイドライン(2017年改訂版)より抜粋(60p))
<高度リスク群(感染しやすく、重症化しやすい患者)>
・人工弁術後
・感染性心内膜炎の既往
・姑息的吻合術や人工血管使用例を含む未修復チアノーゼ型先天性心疾患
・手術,カテーテルを問わず人工材料を用いて修復した先天性心疾患で修復後6 ヵ月以内
・パッチ,人工材料を用いて修復したが,修復部分に遺残病変を伴う場合
・大動脈縮窄
<中等度リスク群(必ずしも重篤とならないが,心内膜炎発症の可能性が高い患者)>
・高度リスク群,低リスク群を除く先天性心疾患(大動脈二尖弁を含む)
・閉塞性肥大型心筋症
・弁逆流を伴う僧帽弁逸脱
<低リスク群(感染の危険性がとくになく,一般の人と同等の感染危険率とされる患者)>
・単独の二次孔型心房中隔欠損
・術後6ヵ月を経過し残存短絡を認めない心室中隔欠損または動脈管開存
・冠動脈バイパス術後
・弁逆流を合併しない僧帽弁逸脱
・生理的,機能性または無害性心雑音
・弁機能不全を伴わない川崎病の既往
(なお、お子さんに比較的高頻度に見られる「心房中隔欠損症」では、感染性心内膜炎のリスクは高くないため予防は不要です)
【予防のために何に気を付けると良い?】
<虫歯の予防>
虫歯(う歯)は感染性心内膜炎の大きなリスクとなります。歯磨き、歯間ブラシを十分に行って虫歯を予防しましょう。かかりつけの歯科医をもち、歯磨き指導を受けたり、定期的に口腔内のチェックや歯石取りなどを行うことが望ましいです。特に歯磨きは、我流でするのとしっかり指導を受けるのとではまるで磨き方が違います。
また、特に1~3歳頃のお子さんは歯磨きを嫌がって泣くかもしれませんが、入念に歯磨きしてあげてください。
<歯科での処置>
歯科では、「感染性心内膜炎の予防が必要な心疾患がある」と伝えてください。歯科で行われる処置(抜歯や、大量の出血を伴う歯石取りなど)によっては事前の抗菌薬投与が必要なことがあります。処置の1時間前に、「アモキシシリン」という抗菌薬を、お子さんの体重1kgあたり50mg内服します。(40kg以上の場合は一律2000mg。成人も一律2000mg)
かなりの大量ですが、前もって抗菌薬を飲んでおくことで感染性心内膜炎発症のリスクを下げることができると考えられています。
<アトピー性皮膚炎>
皮膚からの出血が見られるようなアトピー性皮膚炎の場合も、感染性心内膜炎のリスクと言われています。2020年以降、アトピー性皮膚炎の治療が格段に改善してきています。難治の場合も、プロアクティブ療法などの標準的治療をしっかり受けて、皮膚を良い状態に保つ必要があります。
<ピアス、タトゥー>
お子さんが大きくなったら、おしゃれ目的でピアスやタトゥーをしたがるかもしれません。きちんと清潔な環境で行わないとやはり感染性心内膜炎のリスクとなりますので通常はお勧め致しません。どうしても必要な場合は、美容外科を受診して、感染性心内膜炎のリスクがあることを説明した上で行ってもらってください。
<その他の処置>
歯科治療以外でも、病院で行われる様々な処置において抗菌薬の予防的投与が必要になるものがあります。例えば、扁桃摘出術、アデノイド摘出術などが該当します。
一方で、予防接種、採血、点滴、中心静脈カテーテル挿入などの場合は予防的投与の必要性はないと考えられています。
一般の心臓カテーテル検査の際は、投与を行っても「構わない」、との位置づけです。
(感染性心内膜炎の予防と治療に関するガイドライン(2017年改訂版)より (52p))
【どんな時に感染性心内膜炎を疑う?どうすればよい?】
感染性心内膜炎のリスクがあるお子さんが、長引く発熱、倦怠感がある場合に疑います。咳や鼻水といって風邪の症状、一時的な嘔吐や下痢と言った胃腸炎の症状がある場合は、まず感染性心内膜炎の可能性はありません。(感染性心内膜炎から心不全に至った場合は嘔吐する可能性は考えられます)
長引く熱が見られる場合は、医療機関を受診しましょう。その際も、感染性心内膜炎のリスクがあるということをしっかり伝える必要があります。
医療機関では、抗菌薬を投与する「前に」血液培養検査をすることが重要です。「血液の中に菌がいるのか?」「その場合原因となる菌は何なのか?」ということが分からないと適切な治療ができません。しかし飲み薬の抗菌薬を開始してしまうと中途半端に菌が死んでしまい(でも根治はしない)、上述の重要な情報が得られなくなってしまう可能性があります。
【将来いつまで予防が必要か?】
欠損孔が自然閉鎖した、心室中隔欠損や動脈管開存を手術やカテーテル治療で閉鎖してから6か月以上経過した、などの場合は、予防が必要なくなることもあります。
一方で、多くの先天性心疾患では生涯に渡って感染性心内膜炎の予防が必要となります。お子さんが大きくなってきたら、少しずつ説明してあげて、自立した後も適切な対応が取れるよう教えてあげる必要があります。

いろいろ注意することはありますが、身近なところでは、「虫歯にならない」というのがとても大事なんですね。

そうですね。もちろん感染性心内膜炎のリスクが高くない人であっても虫歯予防はとても重要ですので、しっかり「正しい」歯磨きを身につけましょう。