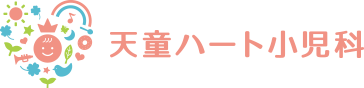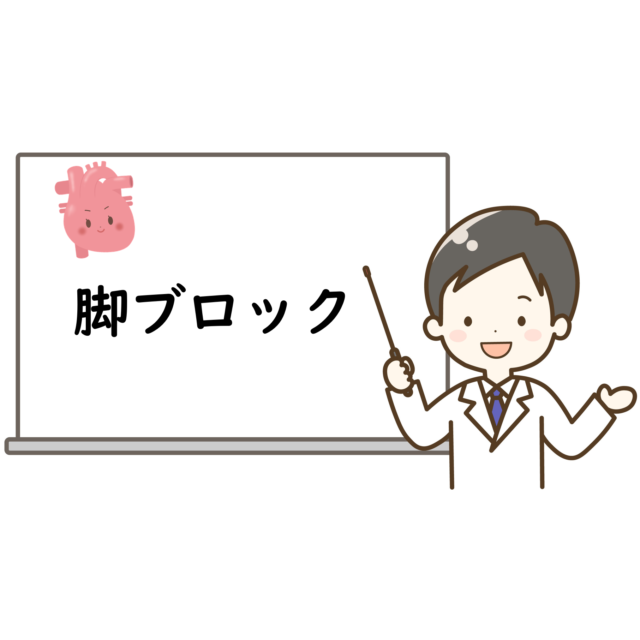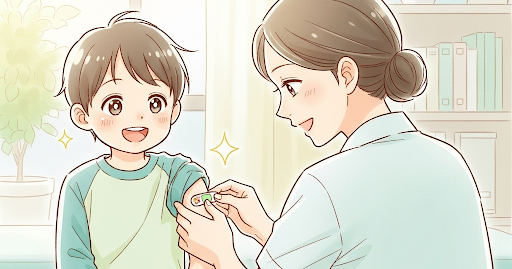先生…。うちの子、これまで一生懸命サッカーをやっていたのですが、心臓に病気があるからこれからは試合には出てはいけないと言われて…。息子も塞ぎこんでしまって、私も悲しくて…。
なんで運動制限をしなくてはいけないんでしょうか?

運動が大好きな年齢で運動制限をかけられると辛いですよね。ご本人も、ご家族も同じ思いだと思います。心臓病における運動制限についてお話していきますね。
【ざっくりと!】
・心臓病の中には、運動を制限しないといけないものがあります。
・その目的は大きく分けて、「突然死を防ぐため」と「病状を悪化させないため」の2つがあります。
・学校(園)から親御さんに渡される「学校生活管理指導表」という用紙に医師が記載をし、親御さんが学校(園)に提出することで情報を共有します。
【どうして運動制限が必要なの?】
主に、「突然死を防ぐため」と「病状を悪化させないため」の2つが大きな目的となります。患者さんによっては、両方の目的を兼ねていることもあります。
<突然死を防ぐため>
・運動によって致死的不整脈が生じる可能性がある
・遺伝性不整脈(QT延長症候群、カテコラミン誘発多形性心室頻拍など)、肥大型心筋症、先天性心疾患の一部など
・大動脈弁狭窄(左心室の出口が狭い)
・肺動脈性肺高血圧
・心臓に血液を送る冠動脈に異常がある(冠動脈奇形、川崎病後冠動脈病変)
・動脈の壁が弱く、激しい運動で血管が破裂したり裂けたりしやすい
など。
これらの病気がある場合、激しい運動中に突然心臓が止まってしまうことがあります。学校心臓健診の広まりと共に日本全国で必要なお子さんに適切な運動制限をするようにしたところ、心臓突然死の発生率が1/4まで低下しました。運動制限は命を守るために必要な場合があるのです。
<病状を悪化させないため>
・生まれつきの心臓病(先天性心疾患)で、運動によって心臓に負担がかかるもの
・短絡があって特定の部位に余計な血液がたくさん流れている
・狭窄があってその手前の部屋で交通渋滞が起こっている
・チアノーゼがあり、運動そのものが負担である
・心室の筋肉に異常があり(心筋症など)、心臓に余力がない
など
これらの病気がある場合、運動をすることで心臓や内臓に負担がかかり、それが蓄積することで将来重大な合併症につながる可能性があります。
もともと健康で運動をたくさんしていた、自覚症状が全くない。そのようなお子さんは、医師から運動制限を指示されるとショックを受けることでしょう。
思い切り体を動かすこと、仲間とプレイして絆を深めることなど、運動による良い効果と言うのは本当にたくさんあります。それを分かった上で、我々も辛い思いをしながら、それでも運動制限を指示しています。それは、患者さんに「絶対死んでほしくないから」、あるいは元気で長生きしてほしいから」に他なりません。
運動が制限されると、体育を見学しなくてはいけなくなったり、スポーツクラブをやめなくてはいけなくなったり、友達と同じ遊びが出来なくなったりして、疎外感や喪失感を感じるお子さんもいらっしゃいます。親御さんは、どうかそのようなお子さんの気持ちに寄り添って、湧いてくるネガティブな気持ちを十分に吐き出させてあげてください。
また、大人に内緒で、あるいはなし崩し的に激しい運動をしてしまい、失神や突然死を起こしてしまうお子さんも実際にいます。なぜ運動制限が必要なのか、を繰り返し説明して、しっかり制限を守ることが重要です。
【具体的にどんな運動制限をするの?】
病状に応じて、どれくらい強い運動制限をするか変わってきます。
日本学校保健会が学校生活管理指導表を公表しており、これに従って運動制限を行います。
https://www.hokenkai.or.jp/publication/guidance.html
各種目ごとにかなり詳しく記載がありますので、どこまで運動をしていいのかの有効な指標になると思います。
以下、重要な点を抜粋します。
②指導区分
・要管理
A . 在宅医療・入院が必要
B. 登校(登園)はできるが運動は不可
C. (同年齢の平均的児童生徒にとっての)軽い運動は可
D. (同年齢の平均的児童生徒にとっての)中等度の運動まで可
E. (同年齢の平均的児童生徒にとっての)強い運動も可
・管理不要
上述の通り、運動制限の程度は、要管理のA~Eと管理不要の6段階となっています。
更に、運動部(クラブ、スポ少なども含む)が可能かどうかも指示します。
(可能な場合は「E可」、可能でない場合は「E禁」とします)
軽い運動、中等度の運動、強い運動は、以下の通り定義づけられています。
<軽い運動(C, D, E, 「管理不要」で可能)>
・同年齢の平均的児童生徒にとって,ほとんど息がはずまない程度の運動.
・球技では,原則として,フットワークを伴わないもの.
・レジスタンス運動(等尺運動)は軽い運動には含まれない.
<中等度の運動(D, E, 「管理不要」で可能)>
・同年齢の平均的児童生徒にとって,少し息がはずむが,息苦しくはない程度の運動.
・パートナーがいれば,楽に会話ができる程度の運動であり,原則として,身体の強い接触を伴わないもの.
・レジスタンス運動(等尺運動)は「強い運動」ほどの力を込めて行わないもの.
<強い運動(E, 「管理不要」で可能)>
・同年齢の平均的児童生徒にとって,息がはずみ息苦しさを感じるほどの運動.
・等尺運動の場合は,動作時に歯を食いしばったり,大きな掛け声を伴ったり,動作中や動作後に顔面の紅潮,呼吸促迫を伴うほどの運動.
基本的に、学校生活管理指導表は1年に1回の更新を行います。学年が変わったら学校生活管理指導表を医院に持参して記載をご依頼ください。
また、特にこれまで運動習慣があった人が突然運動をやめると、肥満や将来の生活習慣病発症のリスクとなります。息の弾まない有酸素湯堂を長時間行うのは問題ないことが多いので、医師の許可が得られるようでしたら、ウォーキングや無理のないハイキング、サイクリングなどは気晴らしもかねてやってみても良いでしょう。

運動制限の重要性が分かりました。現状を受け入れて、可能な範囲の運動を楽しんでいけるよう促してあげたいと思います。

医師や医療スタッフはいつでも、お子さんのより良い人生のためのパートナーでありたいと思っています。お困りのことなどありましたら、遠慮なくご相談下さいね。